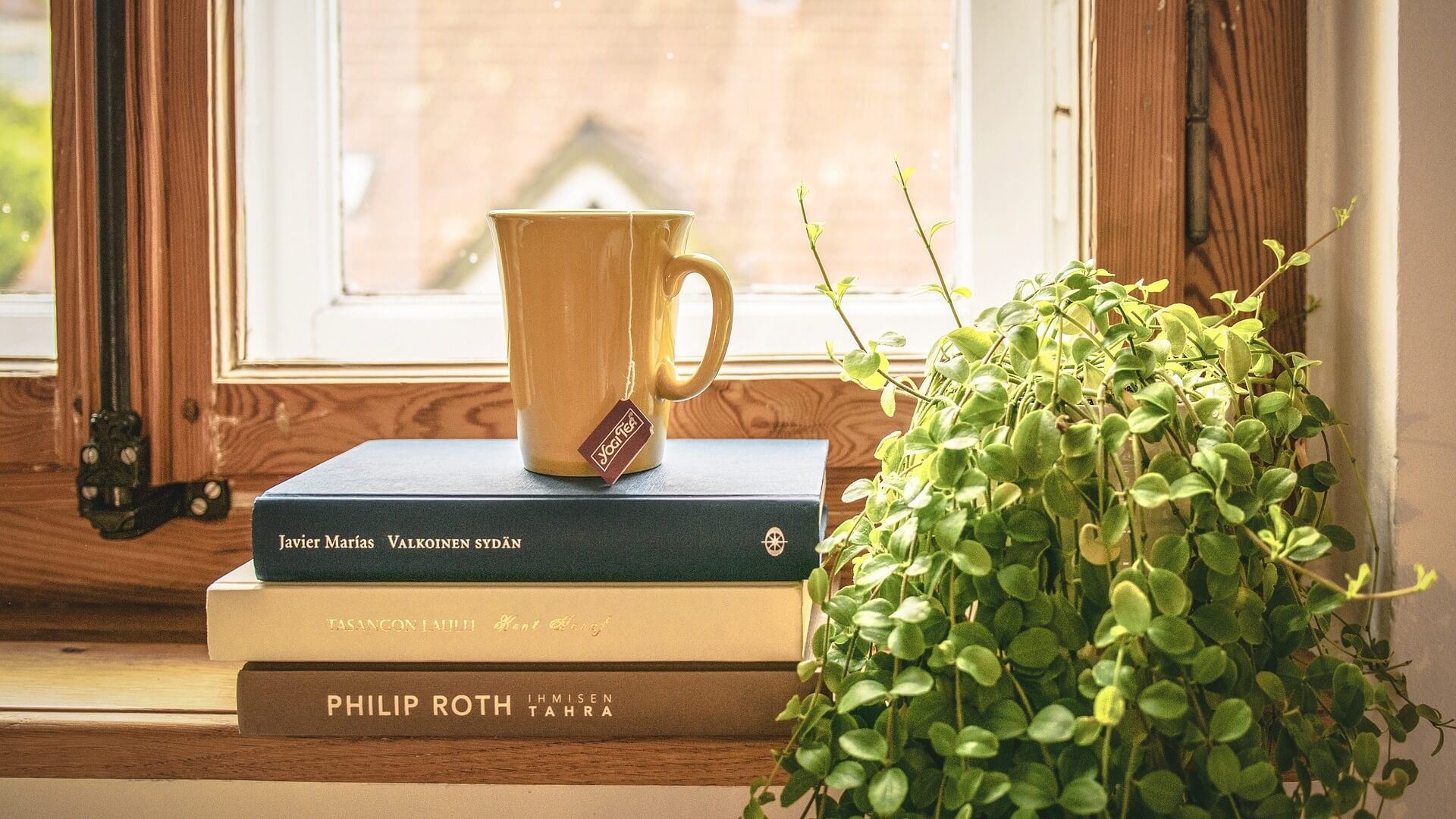精神保健福祉士国家試験合格までの専門科目6科目における学習法を、試験勉強に使用したテキストを中心にご紹介します。
専門学校入学に際して購入した教科書以外、後から買ったのは模擬問題集と過去問のみ。独学で勉強した結果、その年の合格基準点を大幅に上回り国家試験合格を勝ち取りました。
分厚い参考書の類は一切購入していませんし、私の場合は実際に買わなくて良かったと思っています。この記事を読むと、私が独学で合格に至った勉強法について知ることができます。
模擬問題集2冊+過去問1冊 を使用
令和6年度(第27回)以降の専門科目6科目は下記の予定で、全48問で構成される見込みです。
精神医学と精神医療
現代の精神保健の課題と支援
精神保健福祉の原理
ソーシャルワークの理論と方法(専門)
精神障害とリハビリテーション論
精神保健福祉制度論
試験前当時に自分で購入した問題集は以下の3冊です。
- 模擬試験3回分を掲載「精神保健福祉士国家試験模擬問題集〈専門科目〉」 中央法規 2冊
- 直近3年分の過去問を掲載「精神保健福祉士国家試験問題〈専門科目〉解答・解説集」 日本精神保健福祉士協会 へるす出版
模擬問題集の1冊目は、最新版が出る前にブックオフで700円くらいで試しに購入しました。
元の値段が3千円台と高額だったので、中古とはいえ新品同様で大変ラッキーでした。
残りの1冊は、過去3年分の問題と解説集が1冊になっている本を購入しました。
私が受験当時は専門科目のみの模擬問題集や過去問がありましたが、残念ながら現在は取り扱いがないようです。
専門科目のみの受験なら通信講座も選択肢になります。
模擬試験は10月に1回だけ受験しました。
その後、模擬試験の問題と解説冊子も、勉強材料として使いました。
模擬試験を受けるチャンスはもっとあったかもしれませんが、勉強が不十分で点が取れない状態で受けても仕方ないと考えたため私は1回のみにしました。
得点ポイントを確実におさえる
法律や歴史などは、科目をまたがって出題されることがあります。
これらは得点が取りやすいポイントなので、確実におさえておくことをお勧めします。
精神保健福祉法における入院形態や、日本の精神障害者福祉の歴史などは繰り返し出題されるので十分に学習し、理解を深めておく必要があります。
また試験対策だけでなく、精神保健福祉士になったときにも入院形態や精神障害者福祉の歴史は覚えておくべき大切な事柄です。
ただ問題を解くだけではなかなか覚えられないため、体系的に理解が必要な分野は、専門学校で教科書として購入した中央法規のテキストを使って復習をしました。
フリマアプリ、オークションを活用
資格試験のテキストや問題集は、種類もたくさんあり3、4千円台ともなると気軽には買えません。
専門学校の先生は、スクーリングの際に、とにかく早い段階から問題を解くことをアドバイスされていました。具体的には、ネットオークションなどでも過去問が数百円から売っているから購入してどんどん解いていくべきと言われました。
あくまで私の経験談ですが、今後受験される方のご参考になれば幸いです !
独学か通信講座か迷ったら、資料請求して比較してみるのもおすすめです。
こちらでは一発合格までの自主勉強法をご紹介しています。合わせてご覧ください。